こんにちは、『ぅて』です。
今回は学者の戦術のひとつ「計略ゾンビ」についてお話しします。
あらかじめ言っておくと、この戦術を否定する気はありません。私自身も使う場面では使いますし、その有効性は揺るぎません。ただ、「計略ゾンビ=学者」という見方が広がってしまうのは、どうにも落ち着かない気持ちがあります。
計略ゾンビの成立まで
計略ゾンビは比較的新しい戦術です。といっても、もう4〜5年は経ちます。
以前は、一度戦闘不能になって衰弱した状態でさらに倒れると「強衰弱」となり、魔法ダメージが出なくなってしまうため、計略でキープするのは現実的ではありませんでした。
ところが、ジョブマスターや装備の充実で計略の持続時間が5分を超えるようになり、衰弱が回復するタイミングに合わせて改めて計略を入れ直す動きが可能になりました。さらに、計略の着弾ダメージが上がり比較的容易にスリップ上限の1万ダメージを出せるようになったことで、「放置しているだけで削り切れる」状況も生まれたのです。
時間制限の緩いコンテンツでは、この仕様がプレイヤーに大きく有利に働きました。
もともと計略スリップは、全滅後の敵のHP回復フェイズを阻止するための“キープ用の一手”という印象でしたが、今ではお手軽討伐の戦術として昇格してしまった、と言えるでしょう。
強さと手軽さゆえの図式化
計略ゾンビは確かに強力です。PTでもソロでも「もう一度の機会」を作れるし、攻略を安定させる武器になります。
ただ、その便利さ・分かりやすさ・結果の速さが前に出すぎると、「学者=計略ゾンビのジョブ」という図式が固定化されてしまう危うさも感じます。
学者の本来の面白さは、白と黒のグリモアを切り替えながら戦術を練ることにあります。範囲化による支援の厚み、弱体の展開、連携の設計。理解が深まるほど選択肢が増えていき、「次はこうやってみよう」とわくわくできるジョブです。
一方で、いまの時代はタイパやコスパが重視され、「すぐに結果が見える戦術」が好まれる傾向があります。その点で計略ゾンビはとても分かりやすく、着手ジョブの入り口としては“正解”に見えるのも確かです。
ただ――正直、それだけで学者を語られてしまうのは少し寂しい。
発信者としての立場
実は、私がこれまでブログや動画で学者を取り上げた際、計略ゾンビを前提にした立ち回りを紹介したことはありません。(タブンネ)
ここまで述べた懸念が理由でもありますが、同時にそれは私なりの矜持でもあります。発信という行為においては、「学者はもっと多面的に面白いジョブだ」という部分を伝えたいからです。
もちろん、PTでの実戦となれば話は別です。仲間と挑むバトルで、それが討伐成功に直結する一手となるなら、私は迷わず計略ゾンビを使います。戦局を救えるなら、ためらう理由はありません。
だからこそ、冒頭で申し上げた通り――計略ゾンビは否定しないし、使うべき場面では積極的に使う。ただ、それが学者のすべてだと語られるのは違う。それが、いま私が伝えたいことです。
終わりに
計略ゾンビは強力で便利な一枚札です。しかし学者の本質はそこに収まりきるものではありません。
白と黒に合わせた戦闘パートの切り替え、戦術の組み合わせ、状況に応じた引き出しの多さ――それらを積み重ねる過程にこそ学者の面白さがあります。
計略ゾンビをひとつの武器として大切にしつつ、その奥にある多彩な戦術へも目を向けてみてください。学者は研究すればするほど、まだ見ぬ可能性を開いてくれるジョブだと、私は思っています。
そして最後にもうひとつ。計略ゾンビは正直、いつ修正されてもおかしくない戦術です。
古参の方なら、崖下の蜂を一方的に射抜く狩り方をモーグリが制した出来事を覚えているでしょう。
計略ゾンビもまた、それと同じように“有事を与える戦術”として見られている可能性があります。
メルトンのように、敵対心が切れたら効果が切れる仕様に改められても、私たちは甘んじて受け入れなければならないでしょう。
今は見逃されていますが、認知が広がれば修正の可能性も広がる。多くのプレイヤーにとっても、そして私自身にとっても、それは望ましい未来ではありません。だからこそ、計略ゾンビを前面に押し出しすぎないことが、この戦術を長く残すための一番の道なのかもしれません。

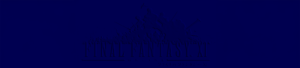
コメント